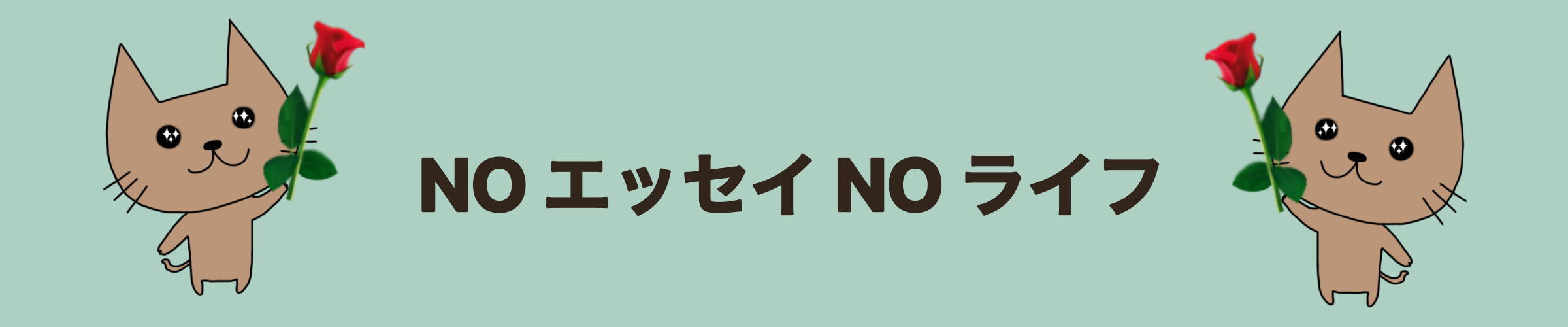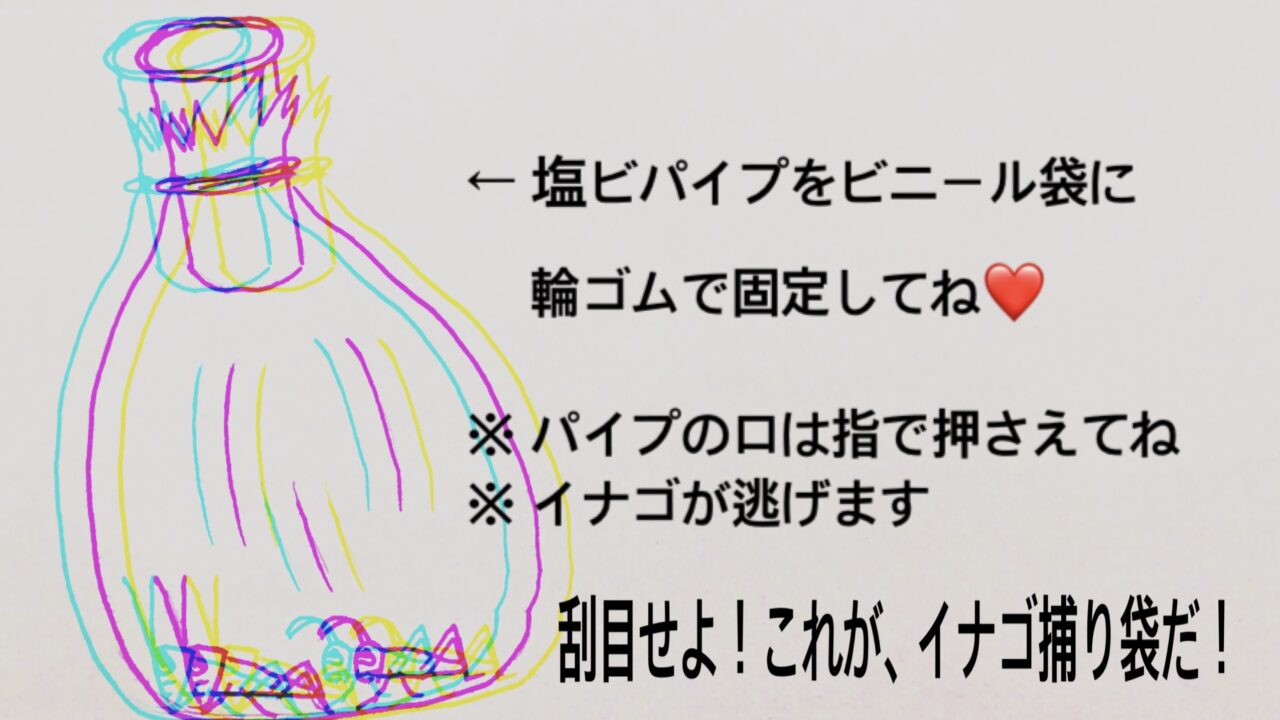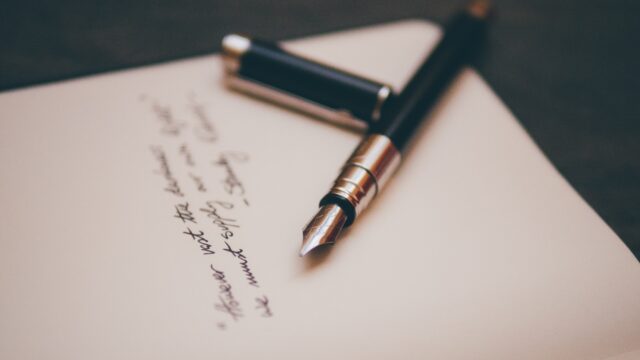こすり倒された質問のひとつに、「無人島になにかひとつ持っていくとしたら?」がある。
ここで、もうひとこすりしよう。
「あなたが無人島にひとつ持っていくとしたら、なんですか?」
サバイバルナイフ、ライター……。
私自身も考えてみたが、イマイチしっくりこない。
これまでに歩んできた人生や、経験のなかにきっと答えが隠されているはず。
私が2歳のとき、父の実家のある田舎へ引っ越し、高校3年生までの16年間を過ごした。
そこは、田舎の中の田舎。
田舎のマトリョーシカだ。
あるいは、田舎の金太郎あめだ。
自然豊かで、空、星、空気もキレイで最高。
自慢の場所だ。
田舎、田舎と書いていたら……。
田舎が「ゲシュタルト崩壊」を起こしてしまった。
もし2歳の私にもっと知恵、力、そしてプレゼン能力があったなら……。
と、アンサーファースト型の完璧なプレゼンで父をねじふせることができたのに。
実家のある田舎や家族には、なんの不満もなくむしろ幸せな思い出しかない私だが、なぜか昔から都会に住みたい。
いや、当然、住むものだと潜在意識にインプットされている。
そのおかげかは定かではないが、やっと首都圏まできた。
方言や見たことのないスナック菓子、全国区だと思っていたチェーン店が関東にはないなど、小さなことから大きなことまで、自分があたりまえだと思っていたことがまったく通用しない。
それが東京砂漠である。
イントネーションは……。
くつ ⤴︎ じゃなく、 くつ →
服 ⤴︎ じゃなく、 服 → だそうだ。
あたりまえではない事のひとつに、保育園での行事がある。
明日は、うれしはずかし「イナゴ捕り」だ。
秋の稲刈りの後という季節限定で、食料調達を兼ねた野あそびに興じる。
それが「イナゴ捕り」だ。
毎年、秋になると父が「イナゴ捕り」にもっていく「イナゴ捕り袋」を作ってくれる。
10cmくらいの塩ビパイプを、ビニール袋に輪ゴムで固定すれば完成だ。
朝早い時間に、父お手製の「イナゴ捕り袋」を引っさげて、クラスみんなで田んぼのあぜ道へ。
「YO!YO! ピー子 is in da house! 」(訳:ヨーヨー、ピー子、登場)
「HEY YO! あつまれ園児!全開だぜ、エンジン!」
「秋のイナゴまつり!捕れなきゃあとのまつり」
「あぜ道にするぜダイブ!熱い心はバイブ!結果しだいでアライブ!」
「引率してくれた先生にマジ感謝」
イナゴを捕まえて、例の「イナゴ捕り袋」にいれる。
イナゴ逃走防止にパイプの口は指で押さえておくのが、上級者のやり方だ。
しこたま捕ったあとは、先生の出番だ。
イナゴをつくだ煮にするのである。
イナゴのつくだ煮の作り方
- 大きな網にイナゴ達をいれ、生かしておいてフンを排出させる。
- 大鍋にグラングランにお湯をわかし、生きたままのイナゴ達を放り込んでゆでる。
まさに、地獄絵図である。
- 1日天日干しにし、羽などをとりさらに2~3日乾燥させる。
- しょうゆ、さとう、水あめをくわえて煮詰めれば完成。
見た目はバッタそのものでグロいが、酒好きにはたまらないつまみだ。
イナゴ以外にも、マムシやきのこ、つくし、蜂の子など野山には食べられるものがたくさんある。
私はこの知識をもって、無人島にいく。
ある哲学者も「知識は力なり」という言葉を残している。
そして、その知識を使って、ナイフやライターに変わるものを作り出せばよい。
ここで、最後にもうひとこすり。
「あなたが無人島にひとつ持っていくとしたら、なんですか?」
私が無人島に持っていく(連れていく)べきは、無人島で一緒にいたい人だ。
よろこびは2倍に、悲しみは半分になるから。